(既読者の方は、冒頭の追加部分だけ、お読みください)
* 「発明塾で書き上げる発明提案書は、何枚程度ですか?」という質問を、何名かの読者の方から、賜りました。発明にもよりますが、(楠浦分含め)過去実績を確認すると、日本語 A4 で 15-25枚、英語 A4 で 10-15枚、でした。
● 「先読み発明」における発明提案書は「設計図/設計仕様書」
既に繰り返しお話をしていますが、
「期日までに、質の高い発明提案書を、必要なだけ出す」
作業を発明塾で6年も継続できたのは、
「”先読み発明”についての発明提案書は、モノづくりに先立つ”設計図”である」
ことを、僕はもちろんですが(元々設計者ですので)、塾生がよく理解してくれていたから、です。
結果として
「設計の仕事に就きたい」
という塾生が出るまでになりました。
「”設計”は究極の”人任せ”の仕事」~発明塾京都第216開催報告
以下に紹介する発明も、「先読み発明」です。
● 「先読み」か否か、で「発明提案書の書き方」は、根本的に異なる
つまり、
「発明提案書の書き方」
は、
「その発明が、先読みか否か」
で、
「根本的に異なる」
ということです。
実験結果を、いかに巧妙に権利化するか、という話は、
e発明塾「発明提案書のための発明の把握法」
に、詳しく記載があります。進歩性を意識して、課題-解決-効果を見直す、という、ある種
「古典的」(必ず身につけておくべき)
手法です。
また、ある発明や先行例にもとづいて、「先読み」発明を創出する手法については、
e発明塾「強い特許のつくり方」
の、後半で取りあげています。コア技術にもとづいて、先読み発明を創出する場合は、
e発明塾「課題解決思考(1)」
の手法をを、利用ください。
いずれにせよ、発明がなければ、発明提案どころの話ではありません。
● しかし、「発明提案書」の中で「発明は育つ」
しかしながら、
「発明は、発明提案書を書く中で育つ」
ことも事実です。
「発明は発明の連続」
であり、終わることがないからです。ここで触れた通りです。
「課題を深堀りする」
「捉え方を変える」
といった、よく言われる話だけでなく、
「構成要素を特定すると、これまでにない”いい感じ”の先行例が見つかる」
からです。弊社主催の「企業内発明塾」参加者の方は、皆さん経験済みだと思います。
「発明を育て、提案書を仕上げる」過程についての詳しい考え方、具体的な手法、および、テンプレート/フォーマット一式は、
e発明塾「発明提案書のための発明の把握法」
に記載があります。発明が提案書を書きながら育っていく、という点は、「先読み発明」でも「実験結果から発明を見出す」場合でも、変わりありません。
==以下、160731以前の内容
以前、エッジ特許の一つとして、
「ヨーグルトが付着しない、ヨーグルト容器の蓋の技術」
についての特許を取り上げました。
ここで取り上げたのは、
「表面微細凹凸を利用した、撥水性付与」
の技術です。発明塾でも度々、フラクタルやナノ構造の持つ、不思議な効果について言及してきました。
しかし、
「表面微細凹凸」
にも、欠点、つまり、課題があります。
「壊れやすい」
は、その一つでしょう。
今回は、過去発明、および、発明討議の紹介を兼ねて、
「耐久性のある微細凹凸表面を、どのようにして実現するか」
について、考えてみましょう。ここで、
「微細表面凹凸 と 耐久性」
が、
「トレードオフ」
であることに注意してください。
あらかじめ技術課題を、トレードオフとして定義できていると、議論が非常に進めやすくなります。
ここに書かれた内容、および考え方を参考に、ぜひ、よりよい発明を生み出してください。
● 微細凹凸を維持する方法は、大きく二つありそう
当時、各自が発明を生み出すために、議論を整理した「マップ」の一例(一部)を、以下に掲載します。
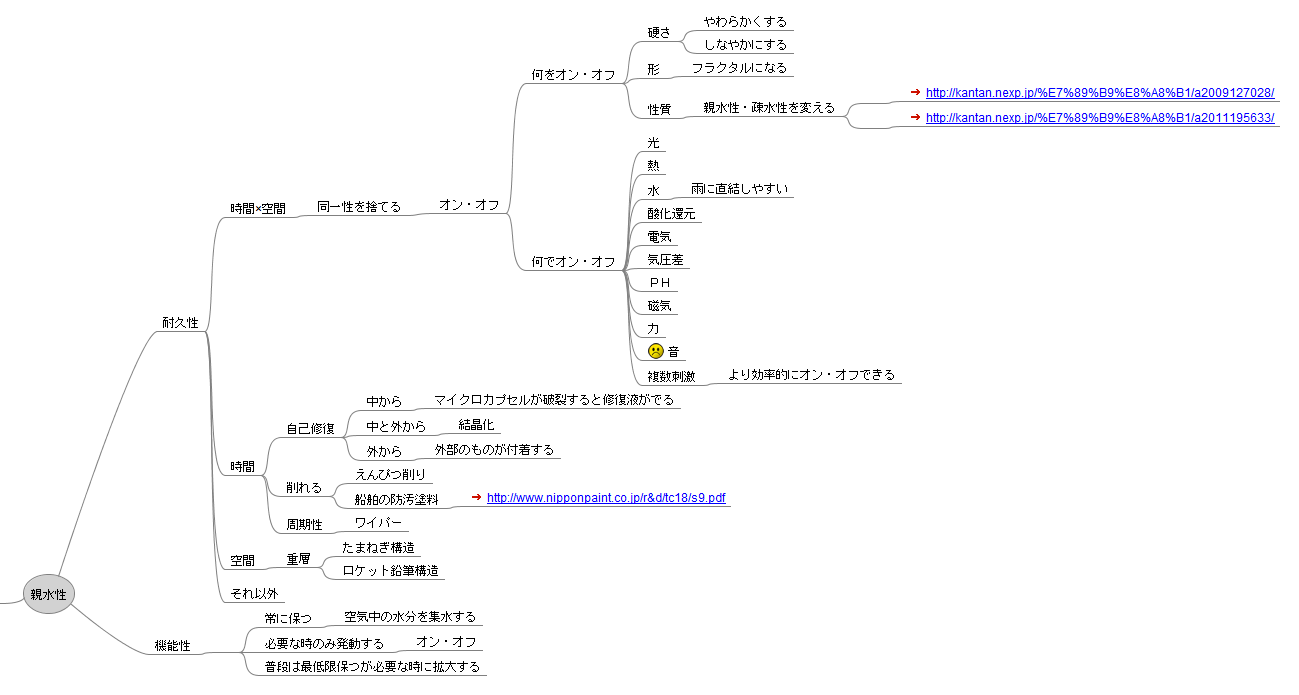
当時の討議資料から抜粋
最近は、みなマップを「飛ばして」議論を行う傾向にありますが、討議の「あるフェーズ」においては、依然として威力を発揮するツールだと思います。
当時既に、楠浦が「時間軸を用いて、撥水性を制御する」というコンセプトの発明を創出していましたので、塾生さんの多くは、
「空間的」
な手法に注目していたようです。アイデアの方向性は、ここで大きく2つに分かれていました。
「凹凸が削れても、次の新しい凹凸が出てくる」(浸食型)
「次々と、新しい凹凸が成長する」(成長型)
「ペプチドナノチューブを用いた、親水・疎水表面」
の発明です。僕の中では
「適当なナノ材料を、混ぜればいいだけなんじゃないの?」
という安易(?)な発想もあったのですが、
「一部のナノ材料は高価」
「そもそもその程度のアイデアは、掃いて捨てるほどある」
わけで、実現するのは、そう簡単ではありません。
今回紹介する発明は、
「ペプチドナノチューブを混ぜる」
という、それだけでも十分新しさがありそうなアイデアについて、もう一歩突っ込んで
「なぜ、この程度のアイデアが、実現されていないのか」
を考える、つまり、
「課題の深掘り」
を行った結果、生まれたものです。
「過去発明の例」
「発明提案書の例」
「課題の深掘りの例」
「ある発明から別の発明へ(特に 制約思考 の一つ Not A 思考)、の例」
など、いくつかの例を兼ねています。
以下、発明塾式
「発明提案」
の基本的な作法の復習も兼ね、順を追って発明を見ていきましょう。
● 「課題の定義」を明確にする
発明、および、発明提案の作成において、もっとも重要なことが「課題の定義」です。
今回の発明では、以下のようになっています。
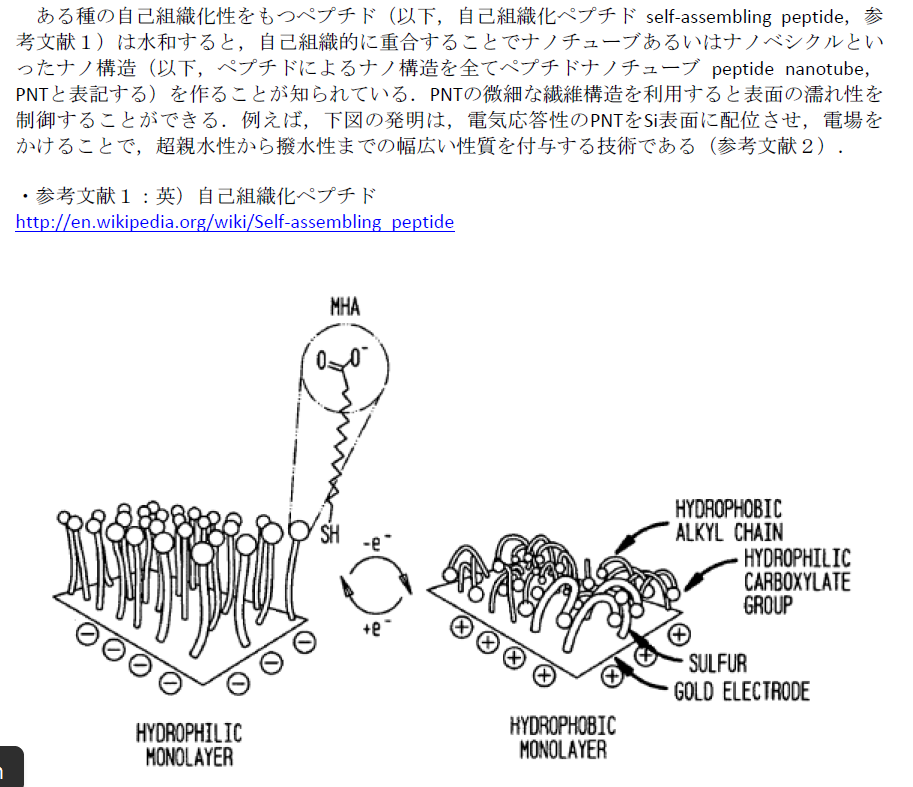
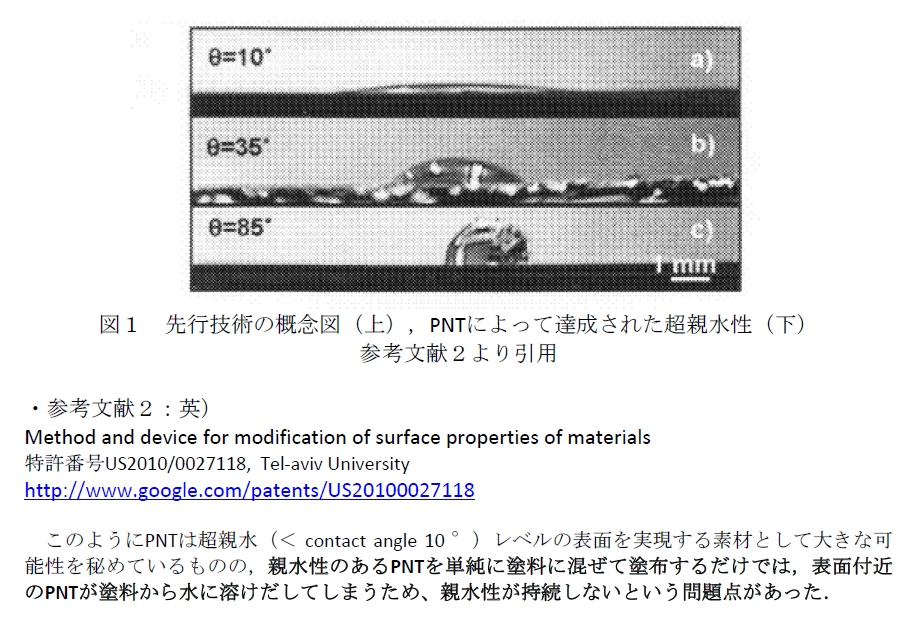
前段で触れたように、
「混ぜるぐらいは誰でも考えるはず、では、なぜそれをやってないのか」
まで、
「一段深く掘り下げ、課題設定」
を行っています。
● 発明の要旨
今回設定した課題に対し、
「要するに、どうするのか」
を、簡潔に記載すると、以下のようになります。
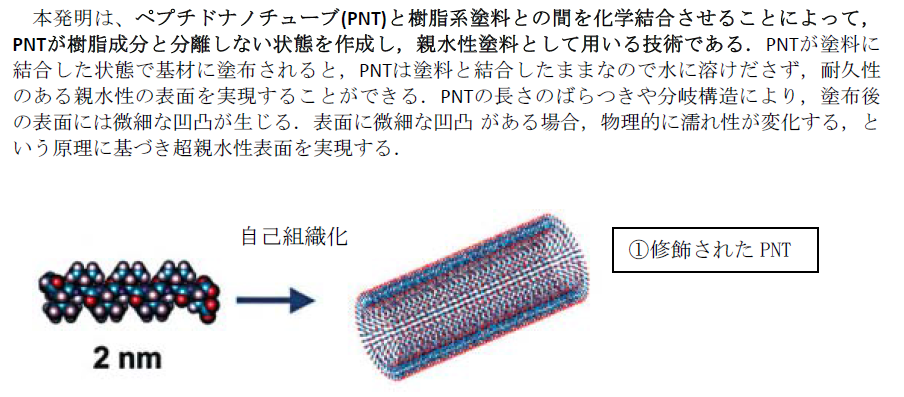
「親水性」塗料を作るために、「親水性」の混ぜ物をするとどうなるか・・・という思考実験のあと、生まれたアイデアです。
「言われてみれば当たり前」
を、どう定義するか、が発明、および発明提案の勘所です。
● 図の重要性
提案書に求められることとして、
「一目で、イメージが掴める」
があります。
ベストかどうかはさておき、当時、塾生さんが頑張った結果、以下の図に落ち着きました。
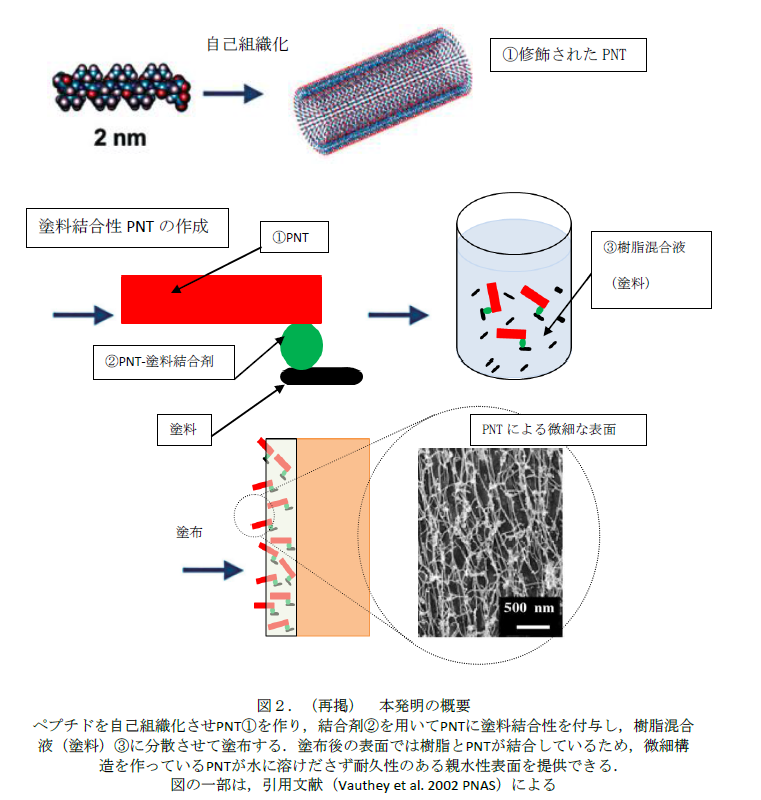
図の下の説明書きも、意外に重要です。
● 原理を押さえる
なぜ、解決できるのか、実験データだけでなく、「原理」つまりサイエンスの部分も、しっかり記載しておきます。
論文ではありませんので、何でもかんでも詳しく書く必要はありません。
「どこまで書くか」、レビュアーの前提知識も睨みながら、書いていきます。
「レビュアーがこの発明を採択したいと思うために、必要十分な情報は何か」
と問い、書き進めます。
今回の発明は、表面積の増大による効果を狙ったものですので、Wenzelの理論について説明しています。
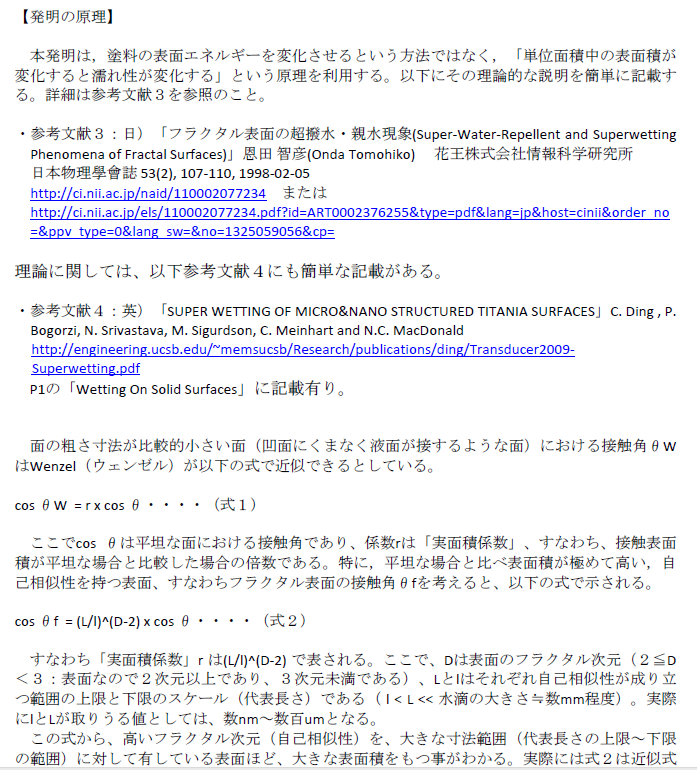
● 発明を構成する要素/それをどう作成するか
発明を構成する要素を、1つ1つ定義し、説明していきます。
まだあまり知られていないと思われるものについては、製造法も記載しておくのがよいでしょう。
「実際、どうやるの?」
という疑問が、レビュアーの頭の中に湧いてくるからです。
今回は、比較的新しい技術である「ペプチドナノチューブ」を用いますので、製造法や種類など、詳しく記載しています。
「ほんとに出来るの?」
「具体的にどうやるの?」
に、答えていきます。
ナノチューブを自己組織化により作成するので、「安価に作成出来る可能性が高い」ことは、一つの特徴でしょう。
そういう意味で、今回の発明において、「製造法」の説明は、重要でした。
また、この点を深掘りすると、更に新しい発明に発展する気がしました。
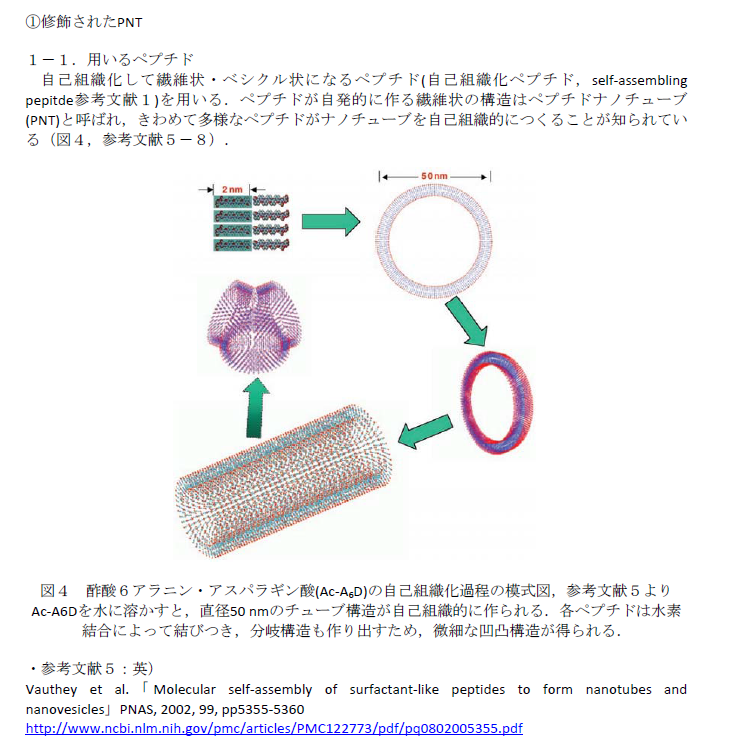
● 発明の効果/競合技術に対する優位性を示す
「単に混ぜるだけでは」のように、想定される従来技術に対する優位性を記載するとともに、他の親水性塗装がどのようなものか、具体的な例を挙げるか、少なくとも想定して、違いを明確にしておきます。
「(ナノ材料)作成の簡便性」も、挙がっていますね。
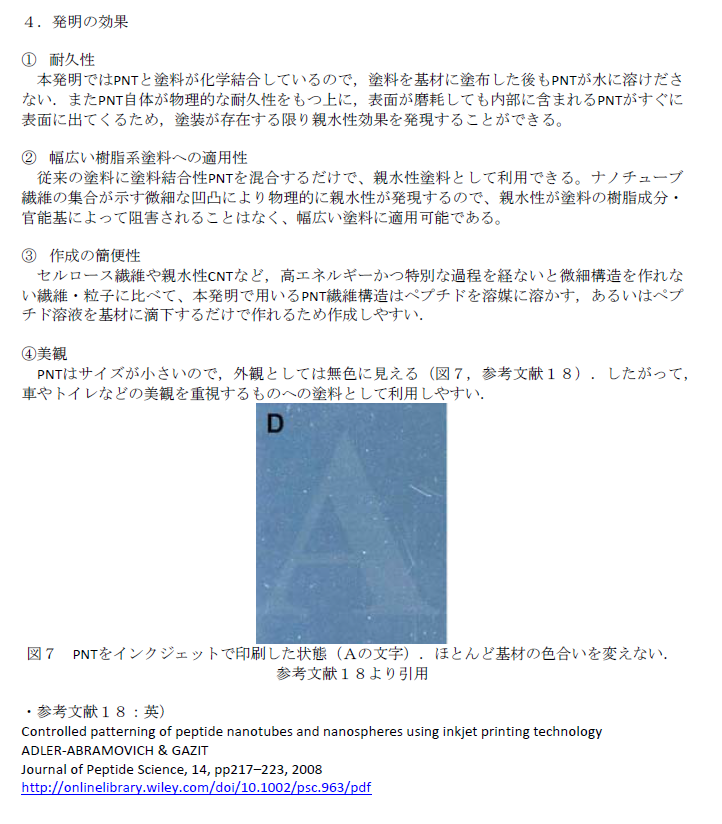
● 他にどのような用途/構成があり得るか
発明の本質を逸脱しない範囲で、
「他に、どのような用途があるか」
「どのような機能を付与できるか」
「構成の一部を、変更するとどうなるか」
などについても、記載しておきます。
今回は、撥水性塗装への転用なども、含めました。
要注意な点は、
「あくまでも、付け足しである」
ということです。用途や構成が変化すると、冒頭で定義した「課題」が変わる可能性がありますが、何でもかんでも含まれるように書こうとすると、
「結局、何が課題だったのか」
よくわからなくなります。
(そうなる人が、大勢います)
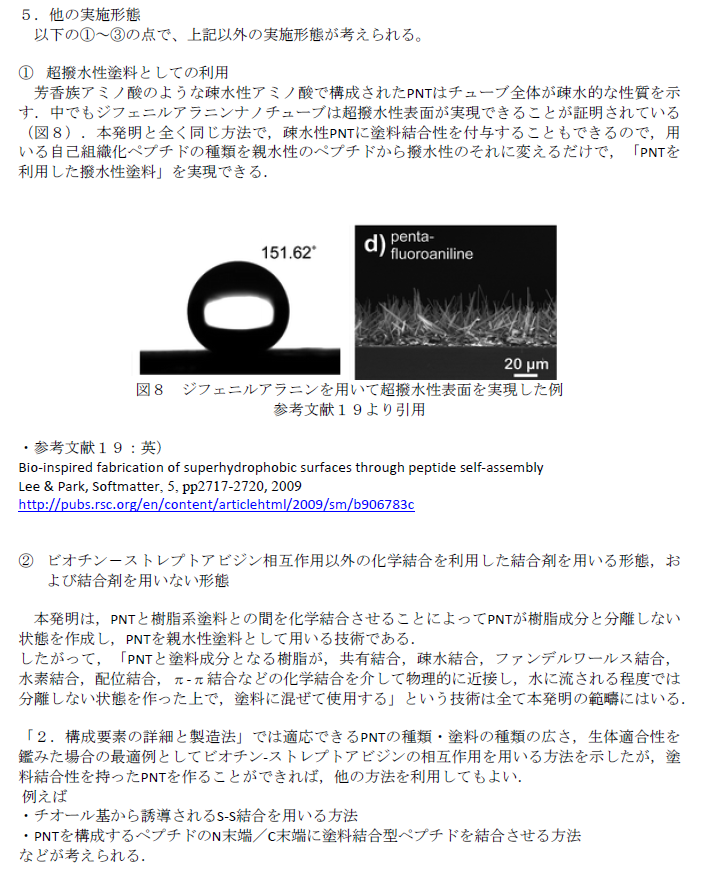
● 「課題」以前の話は「背景」として、まとめておく
繰り返しですが、「課題」をどう定義するか、は、発明/発明提案の本質です。
今回は、
「親水性塗料実現のために、ペプチドナノチューブを混ぜたいとみんな思うはずなんだけど、実は・・・」
というところから始めています。
したがって、
「親水性塗装には、そもそもこういう課題があって・・・」
という話は、
「背景」
として、まとめておきます。どちらも「課題」ですので厄介ですが、
「今回の発明が解決している、もっとも具体的な課題は何か」
が、発明提案における「課題」であり、それ以外は「背景」だと、考えておいてください。
正確には、
「今回の発明において、先行技術にない構成要素があります」
「その構成要素があることにより、はじめて解決できる課題は、XXXです」
のように考えるとよいでしょう。
自身の発明「固有」の「(解決している)課題」、と呼ぶこともできます。
「今回の発明が解決している、もっとも具体的な課題は何か」
が、発明提案における「課題」であり、それ以外は「背景」だと、考えておいてください。
正確には、
「今回の発明において、先行技術にない構成要素があります」
「その構成要素があることにより、はじめて解決できる課題は、XXXです」
のように考えるとよいでしょう。
自身の発明「固有」の「(解決している)課題」、と呼ぶこともできます。
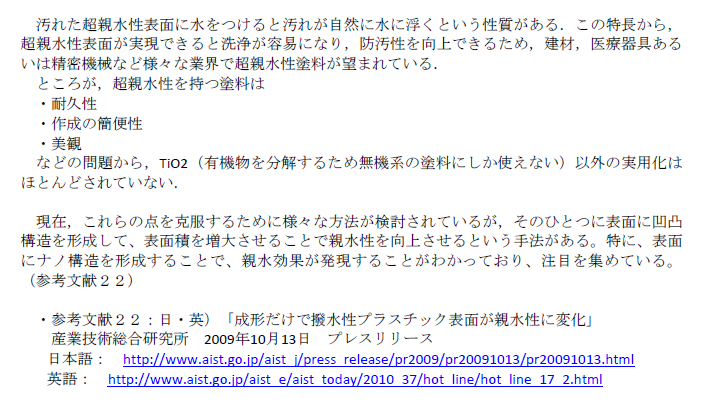
● 参考文献を示す
外国企業への提案、または、外国出願を見据え、参考文献は英語を中心にするか、日英併記にしておきましょう。
リンクが「テンポラリー(一時的)」なものでないか、注意しましょう。
過去、IPDLで頑張って調べた特許のリンクを、大量に貼ってくれた塾生さんがいました。
残念ながら、すべて一時的なリンクであったため、結局全て、別のデータベースで調べ直し、リンクを貼り直してもらうことになりました。
パーマネント(永久)リンクが生成されない調査ツールは、使わないほうが賢明です。
そういうツールは、(自他の)知的生産性を著しく下げます。
言い方は悪いですが、
「組織の足を引っ張る」
と考えられますので、注意しましょう。
言い方は悪いですが、
「組織の足を引っ張る」
と考えられますので、注意しましょう。
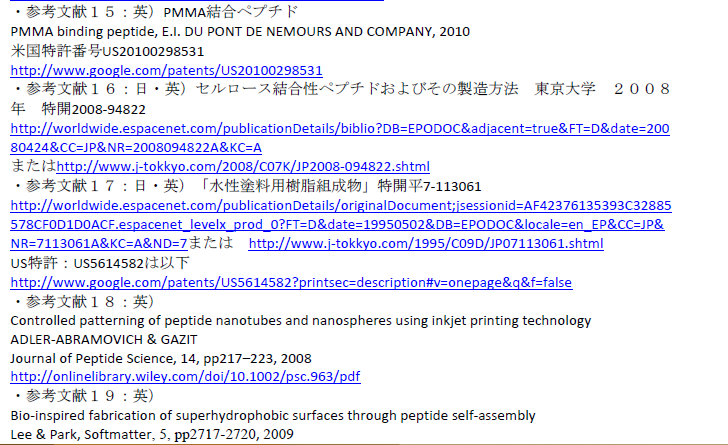
● 「確信がもてる」までロジックを練る
提案書のコツは、
「言葉50-70%」(面積的な話です)
「図表30-50%」(面積的な話です)
を目安として、
「図表を”言葉”で説明し、説明した”言葉”を、再度図表にまとめていく」
ことです。
図表にすることで構造化が進むはずですが、図表にする時に「なんとなく」「ふわっと」になってしまい、ロジックが抜け落ちる危険性があります。
「図にして、再度言葉で説明する」を繰り返し、「ロジックがあり、見やすい、わかりやすい資料」にまとめていきます。
つまり
「図 ⇒ 文章 ⇒ 図 ・・・」
の繰り返しで、練り上げていきます。
これは「自分の頭を整理」し、「確信を持って提案を行う」ためです。
もちろん、その結果として、「周りの人にわかりやすい」という、大きな効果が得られます。
以上、過去発明を振り返り、また、発明提案書の書き方を復習しました。
提案書のコツは、
「言葉50-70%」(面積的な話です)
「図表30-50%」(面積的な話です)
を目安として、
「図表を”言葉”で説明し、説明した”言葉”を、再度図表にまとめていく」
ことです。
図表にすることで構造化が進むはずですが、図表にする時に「なんとなく」「ふわっと」になってしまい、ロジックが抜け落ちる危険性があります。
「図にして、再度言葉で説明する」を繰り返し、「ロジックがあり、見やすい、わかりやすい資料」にまとめていきます。
つまり
「図 ⇒ 文章 ⇒ 図 ・・・」
の繰り返しで、練り上げていきます。
これは「自分の頭を整理」し、「確信を持って提案を行う」ためです。
もちろん、その結果として、「周りの人にわかりやすい」という、大きな効果が得られます。
以上、過去発明を振り返り、また、発明提案書の書き方を復習しました。
なお、本稿記載の発明提案書は、京都大学大学院(当時) 菅野 茂夫 さん 作成のものです。
後進の育成と、よりよい発明創出のため、協力をお願いしたところ、快諾いただきました。
菅野さん、ありがとう。
楠浦 拝